オールジャンル一行問題
東京帝国大学(1935年/(農)第3問)
$x^{x^{x}}$を微分せよ。
国際数学オリンピック ルーマニア大会(1959年/第1問)
Prove that the fraction $\dfrac{21n+4}{14n+3}$ is irreducible for every natural number $n$.
和訳:すべての自然数$n$に対して$\dfrac{21n+4}{14n+3}$が既約分数であることを示せ。
名古屋大学(1965年/理系第2問)
$1$辺の長さが$a$の正三角形の面積を$2$等分する線分のうちで最も短いものの長さを求めよ。
名古屋大学(1966年/理系第4問)
和が$1$である無限等比級数の第$n$項がとりうる値の範囲を求めよ。
名古屋市立大学(1967年/前期第1問(1))
正弦定理を述べて、これを証明せよ。
東北大学(1968年/前期(教育)第5問)(問題文の表現を一部変更)
$y=1-|x|$に接し、$y$軸を軸とする上に凸な放物線で、$x$軸と囲む面積が最大になるものを求めよ。
一橋大学(1968年/2次選抜試験/第2問)
だ円$x^2+4y^2-4x+8y+4=0$が、傾き$1$の直線から切り取る線分の長さの最大値を求めよ。
一橋大学(1968年/2次選抜試験/第4問)
$\log_{10} 2$は有理数でないことを証明せよ。
東京工業大学(1968年/前期第5問)
次の極限値を求めよ。 $\displaystyle \lim_{n \to \infty} \dfrac{1}{n} \sqrt[n]{{}_{2n}\mathrm{P}_{n}}$
名古屋市立大学(1968年/(医/薬)第1問)
等式 $\displaystyle \lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}=1$ を証明せよ。
一橋大学(1970年/2次選抜試験/第1問)
$\sin x+\cos x =0.8$ のとき、$\sin 3x-\cos 3x$の値を求めよ。
大阪市立大学(1972年/理系前期第2問)
$6$乗してはじめて$1$になる複素数を求めよ。
名古屋市立大学(1975年/前期第2問)
連続した正の整数からなる数列の和が$1000$に等しいという。このような数列をすべて求めよ。
名古屋大学(1977年/前期共通第3問)
関数$y=\dfrac{1}{x}$のグラフ上の$2$点を結ぶ線分の中点となるような点全体の集合を図示せよ。
東北大学(1980年/前期(教育)第2問)
原点$\mathrm{O}$から直線 $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{4}=\dfrac{1-z}{5}$ に下ろした垂線の長さを求めよ。
東京工業大学(1988年/前期第5問)
$\displaystyle \lim_{n \to \infty} \left(\dfrac{{}_{3n}\mathrm{C}_{n}}{{}_{2n}\mathrm{C}_{n}}\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めよ。
お茶の水女子大学(1988年/前期/(数)第4問/(物理)第2問)
$3^x-2x^2-1=0$ の異なる実数解の個数を調べよ。
東京工業大学(1989年/前期第4問)
次の極限値を求めよ。 $\displaystyle \lim_{n \to \infty} \int^{\pi}_{0} x^2 |\sin nx| dx$
お茶の水女子大学(1989年/前期(数)第2問)
$\displaystyle \lim_{x \to \infty} \int^{x}_{0} |\sin t| e^{-t} dt$ を求めよ。
大阪大学(1990年/前期文系第3問)
点$(1,0)$を通り、曲線 $y=x^4-2x^2+1$ に接する直線の方程式をすべて求めよ。
お茶の水女子大学(1991年/前期理系第3問)
半径$1$の球に内接する正四面体の$1$辺の長さを求めよ。
※2005年北海道大に同一の出題あり
東京工業大学(1993年/後期第1問)
一辺の長さが1の立方体を,中心を通る対角線のうちの一本を軸として回転させたとき,この立方体が通過する部分の体積を求めよ.
※問題文はやや長めですが類題多数の問題ということで掲載します。
名古屋大学(1994年/前期理系第4問(b))
長方形に置かれた三角形の面積は,もとの長方形の面積の$\dfrac{1}{2}$を越えないことを示せ。
お茶の水女子大学(1995年/(数)前期第7問)
$\dfrac{100}{120}< \sin 1 <\dfrac{101}{120}$ を示せ。ただし、$\sin 1$ の $1$ はラジアンの意味である。
お茶の水女子大学(1998年/(数)前期第6問)
$\tan 50^{\circ} \tan (90^{\circ}-x)=\tan 80^{\circ} \tan (50^{\circ}-x)$ の解を求めよ。
千葉大学(1999年/前期第9問((数学情報)第5問))
$8n^3+40n$が$2n+1$で割り切れるような正整数$n$をすべて求めよ。
東京工業大学(1999年/後期第1問)
次の極限値 $\displaystyle \lim_{n \to \infty} \int^{\frac{\pi}{2}}_{0} \dfrac{\sin^2 nx}{1+x} dx$ を求めよ。
お茶の水女子大学(1999年/前期理系第1問)
$a$を定数とするとき、$|x|+2|y|=2$ と $y=\dfrac{1}{4}x^2-a$ の交点の個数を求めよ。
お茶の水女子大学(1999年/(数)前期第4問)
$n$を正整数とする。$2^n+1$ は$15$で割り切れないことを示せ。
一橋大学(2001年/後期第1問)
$m$を正の整数とする。$m^3+3m^2+2m+6$はある整数の$3$乗である。$m$を求めよ。
和歌山大学(2001年/前期(システム工?)第1問)(数学簿記)
区分式の損益計算書の構造について説明し、その意味を解説しなさい。
東京大学(2003年/前期理系第6問)
円周率が$3.05$より大きいことを証明せよ。
京都大学(2003年/後期文系第5問/後期理系第6問)
多項式$(x^{100}+1)^{100}+(x^2+1)^{100}+1$は多項式$x^2+x+1$で割り切れるか。
京都大学(2003年/後期理系第5問)
次の極限値 $\displaystyle \lim_{n \to \infty} \sum^{2n}_{k=1} (-1)^k \left(\dfrac{k}{2n}\right)^{100}$ を求めよ。
第14回日本数学オリンピック(2004年/本選第1問)
$2n^2+1$、$3n^2+1$、$6n^2+1$がどれも平方数であるような正整数$n$は存在しないことを示せ。
北海道大学(2005年/前期文系第4問/前期理系第5問)
半径$1$の球に内接する正四面体の一辺の長さを求めよ。
※1991年お茶の水女子大(理系)に同一の出題あり
和歌山県立医科大学 (2006年/前期第2問)
自然数$n$に対して、$\displaystyle \sum_{k=1}^{12n-1} \left( \cos \dfrac{k \pi}{12} \right)^2$ を求めよ。
京都大学(2006年/後期文系第5問/後期理系第6問)
$\tan 1^{\circ}$は有理数か。
国際数学オリンピック ベトナム大会(2007年/第5問)
Let $a$ and $b$ be positive integers. Show that if $4ab-1$ divides $(4a^2-1)^2$, then $a=b$.
和訳:$a、b$を正の整数とする。$4ab-1$が$(4a^2-1)^2$を割り切るならば$a=b$であることを示せ。
和歌山県立医科大学 (2006年/前期第2問)
$f(x)=(\sin x)^2+(\sin 2x)^2$ の $0<x<\pi$ における極値を求めよ。
日本獣医生命科学大学(2008年/(獣医)第2問)
多項式$P(x)$は $P(P(x))=P(x^2)$ を満たしている。このとき$P(x)$をすべて求めよ。
一橋大学(2009年/前期第1問)
$2$以上の整数$m、n$は $m^3+1^3=n^3+10^3$ を満たす。$m、n$を求めよ。
第19回日本数学オリンピック(2009年/本選第1問)
$8^n+n$が$2^n+n$で割りきれるような正の整数$n$をすべて求めよ。
名古屋市立大学 (2010年/(芸術工)前期第1問)
方程式 $2 x \sin x-3=0\ (-\pi \leqq x \leqq \pi)$ の解の個数を求めよ。
和歌山県立医科大学 (2011年/前期第1問)
等式 $|x-2y|=y+\sqrt{1-x}+1$ を満たす整数の組$(x, y)$をすべて求めよ。
千葉大学(2013年/前期第9問(理系第5問))
$m^4+14m^2$が$2m+1$の整数倍となるような整数$m$をすべて求めよ。
千葉大学(2013年/前期第10問((数学情報)第6問))
$\tan {10}^{\circ}=\tan {20}^{\circ} \cdot \tan {30}^{\circ} \cdot \tan {40}^{\circ}$ を示せ。
東京工業大学(2013年/前期第3問)
$k$を定数とするとき、方程式 $e^x-x^e=k$ の異なる正の解の個数を求めよ。
信州大学(2013年/後期(医)第1問)
方程式 $a \cdot 2^x-x^2=0$ が異なる$3$つの解を持つような実数$a$をすべて求めよ。
奈良教育大学(2013年/(教育)第5問)
三角形の$3$辺の垂直二等分線は$1$点で交わることを証明せよ 。
岡山大学(2013年/前期理系第1問)
曲線 $y=\left| x-\dfrac{1}{x} \right| \ (x>0)$ と直線 $y=2$ で囲まれた領域の面接$S$を求めよ。
大阪大学(2014年/前期第3問)
$\displaystyle \sum^{40000}_{n=1} \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ の整数部分を求めよ。
第24回日本数学オリンピック(2014年/本選第2問)
$2^a+3^b+1=6^c$ をみたす正の整数の組$(a,b,c)$をすべて求めよ。
宮城大学(2015年/前期(事業構想(デザイン情報))第1問/問2)
$\log_{10}2 < 0.31$ が成り立つことを示しなさい。
東京大学(2015年/前期理系第5問)
$m$を$2015$以下の正の整数とする。${}_{2015}\mathrm{C}_m$が偶数となる最小の$m$を求めよ。
信州大学(2015年/前期(教育)第4問)
$\sqrt{2}<e^{\frac{1}{e}}$ を示せ。
奈良教育大学(2015年/(教育)第1問)
一辺の長さが$a$の正四面体$\mathrm{ABCD}$の体積を$a$で表せ。
第25回日本数学オリンピック(2015年/本選第1問)
$\dfrac{10^n}{n^3+n^2+n+1}$ が整数となるような正の整数$n$をすべて求めよ。
愛媛大学(2016年/前期(医)第5問)
正方形$\mathrm{ABCD}$の内部の点$\mathrm{P}$に対して$\angle \mathrm{CPD}$が直角であるとき、$\dfrac{\mathrm{BP}}{\mathrm{AP}}$の最大値を求めよ。
一橋大学(2017年/前期第3問)
$P(0)=1$、$P(x+1)-P(x)=2x$ を満たす整式$P(x)$を求めよ。
京都大学(2018年/前期文系第3問/前期理系第2問)
$n^3-7n+9$ が素数となる整数$n$をすべて求めよ。
香川大学(2019年/(医)第2問)
$0<x<1$ において、$1-x^2$、$\sqrt{1- x^2}$、$\cos x$ の値の大小を比較せよ。
京都大学(2021年/前期理系第3問)
無限級数 $\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n} \cos \frac{n \pi}{6}$ の和を求めよ。
京都大学(2021年/前期理系第4問)
曲線 $y=\log (1+\cos x) の 0 \leqq x \leqq \frac{\pi}{2}$ の部分の長さを求めよ。
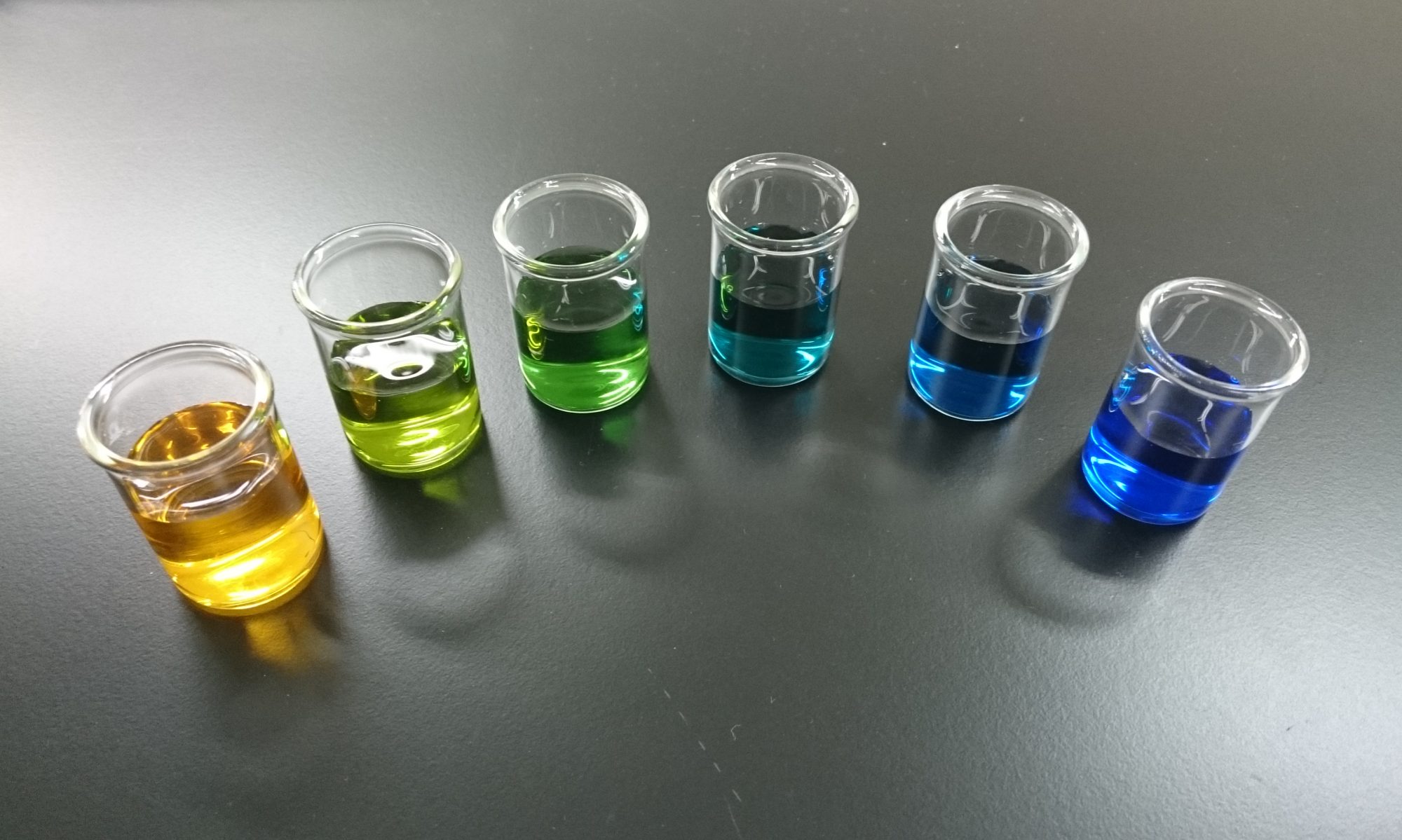
主に、見た目からは想像しにくい解法を要求してくる問題や、方針は立つけれど少し工夫や閃きが必要な問題を集めているつもりです。また、60~70年代以前の高校数学では、単元の区分や大学入試における出題様式が現行課程と比較して大きく異なるため、なるべく興味深い問題を選んで蒐集するよう心掛けています。(一部、1行に収まりきってない問題もありますが、問題冊子に印字すれば1行になるはずです・・・)
いつの時代でも一行問題は受験生の肝を冷やすものですが、ヒントが少ないからこそ本物の数学力が試されている問題であるということは言うまでもありません。やはり問題文はただ長ければ良いってもんじゃないですよね(笑)。
なお、小問集合のように細かい問題を多数出題する大学の入試では一行問題のオンパレードとなりますが、一行問題はたまに出題されるからこそ価値があるのです。・・・ということで、そういった大学の問題は特段の事情が無い限り掲載していません。悪しからず・・・。